「2025年7月5日、安全な場所はどこ?」——そんな検索をしたあなたは、すでに何か胸騒ぎや情報に触れているのではないでしょうか。
一部では地震や異変、スピリチュアルな予言など、さまざまな情報が交錯しています。
本記事では、2025年7月5日に何が起きるとされているのか、そして万が一の備えとして注目される「安全な場所」について、地理的・災害リスク・精神的観点から解説します。
なぜ「2025年7月5日」に注目が集まっているのか?
|
|
SNSや予言界隈で囁かれる「異変の日」

2024年後半から、SNSやスピリチュアル系のコミュニティを中心に、「2025年7月5日に大きな地震やエネルギーシフトが起きる」という話題が急浮上しています。
以下のような情報が一部で共有されています。
- 南海トラフ地震の予兆とされる異常現象
- スピリチュアル系YouTuberによる予言動画
- 天体配置(占星術)による社会的混乱の暗示
- 古代文明や預言書に登場する「2025年」というキーワード
現時点では科学的根拠があるわけではありませんが、不安が広がる背景には、情報過多な現代における『集合的な無意識の反応』があるとも言えるのではないでしょうか。
科学的に見た「災害の可能性」とは?

地震リスクに関する公式見解
政府の地震調査研究推進本部は、南海トラフ地震について「今後30年以内に70〜80%の確率で発生する」としています。
特に太平洋プレート沿いのエリア(静岡〜四国〜九州沿岸)は、地震や津波のリスクが高い地域です。
近い将来の発生の切迫性が指摘されている大規模地震には、南海トラフ地震、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首都直下地震、中部圏・近畿圏直下地震があります。
中でも、関東から九州の広い範囲で強い揺れと高い津波が発生するとされる南海トラフ地震と、首都中枢機能への影響が懸念される首都直下地震は、今後30年以内に発生する確率が70%と高い数字で予想されています。
また、2025年は地震の周期説とも一定の関係性が指摘されており、専門家の一部からは「注意が必要な年」とされています。
「不安」が集団心理として拡大する理由
人は「〇〇年〇月〇日」という具体的な日付が提示されると、それが真実かどうかに関係なく、潜在意識の中で強く印象付けられる傾向があります。
これにより、以下のような現象が発生します。
- 無意識のうちに情報を“集めすぎる”
- 自分と家族の未来に不安を抱く
- 本来必要以上の行動を取ってしまう
こうした心理が拡大し、「安全な場所」というワードが急激に検索される流れへとつながっているようです。
「安全な場所」とは?3つの視点で考える

①地理的リスクから見た安全地域
以下は、過去の地震・津波データや地質リスクから見て「比較的安全」と言われる日本国内の地域です。
| 地域名 | 特徴 |
|---|---|
| 長野県北部 | 内陸型で津波の心配がなく、地盤が安定 |
| 岐阜県飛騨地方 | 活断層が少なく、標高が高いため洪水リスクも低い |
| 山梨県甲府市周辺 | 地盤が強く、災害被害が過去比較的少ない |
| 北海道の道東地域 | プレート境界から遠く、大規模地震の可能性が低い |
| 秋田県・山形県内陸 | 豪雪地域だが地震の被害は少なめ |
②社会インフラと防災意識の高さ
安全な場所は地理だけでなく、その地域の防災体制・復旧力・住民の意識の高さも重要です。
例えば:
- 自治体のハザードマップが定期的に更新されている
- 避難訓練が活発に行われている
- 水・電気などライフラインの備蓄支援が整っている
地方自治体の防災情報をチェックして、移住や一時避難の参考にするのも有効です。
③スピリチュアル視点から見た「波動の高い場所」
一部のスピリチュアル界隈では、「波動の高い土地=守られやすい」とされる考え方があります。
具体的には以下のような場所が挙げられるのではないでしょうか。
- 神社仏閣が多く、自然との共存がある地域
- 古くから“聖地”とされる土地(出雲、熊野、戸隠など)
- 人が穏やかで争いが少ない土地
もちろん科学的根拠はありませんが、「安心して心が落ち着く場所」は、いざという時に冷静な判断がしやすいのかもしれません。
今からできる「自分を守る行動」
どんなに場所を選んでも、「備え」がなければ意味がありません。
以下は今からできることを紹介していますので、参考になれば幸いです。
大切なのは「不安を煽られる」のではなく、「備えることで安心を得る」ことです。
|
|
安全を確保するための事前準備ガイド
「安全な場所」を選んでも、準備が不十分ではその効果は半減します。ここでは、緊急時に必要な持ち物リストと避難計画の作り方を紹介します。
必要な準備リスト
- 食料・水(最低3~7日分)
非常時にはライフラインが途絶える可能性があるため、最低3日分の飲料水と非常食を用意しておきましょう。 - 医薬品・常備薬
家族の中に持病のある方がいる場合、必ず常備薬や応急処置用品を携帯することが重要です。 - 防災用品(懐中電灯、ラジオ、モバイルバッテリーなど)
停電時や通信が途絶えた際に役立つツールを備えておくと、状況を把握しやすくなります。
非常時は水が使えなくなる可能性が高いので、必ず非常用トイレの準備はしておきましょう。
目安は1人あたり1日5回トイレをする想定で7日分、計35回分(1人あたり)。
|
|
避難計画の作り方
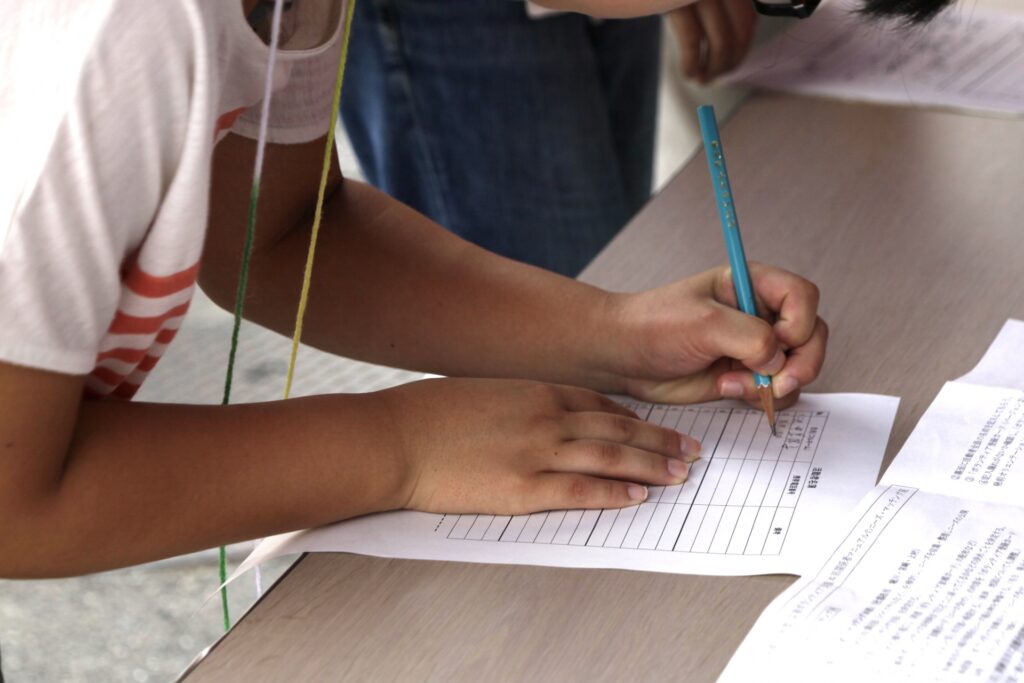
- 家族での連絡方法を決める
緊急時に家族がバラバラになった場合、どのように連絡を取り合うか事前に話し合っておきましょう。 - 避難経路と避難場所を確認する
自宅や職場からどのルートで避難するか、また避難先としてどこが安全なのかを事前に確認しておきます。特に、地図を活用して家族全員が認識していることが重要です。
最新情報の確認方法とリスクの変化に対応するためのツール
災害や社会的リスクは、日々刻々と変化します。そこで、常に最新の情報を得るためのツールやウェブサイトを活用することが大切です。
◎気象庁や自治体の防災アプリ
気象庁や自治体が提供するアプリでは、緊急速報や災害情報をリアルタイムで受け取ることができます。
・特務機関NERV防災アプリ
・気象庁|防災情報
◎緊急速報メールの登録
緊急事態が発生した際に、自動的にスマートフォンへ送信される緊急速報メールを活用しましょう。自治体のホームページなどで登録できます。
◎信頼できるニュースサイトの活用
事前に信頼できるニュースサイトを確認しておき、最新の情報が得られるようにしておくことも有効です。
まとめ
2025年7月5日が近づくにつれ、不安感が増すかもしれませんが、しっかりとした準備と情報収集があれば、落ち着いて対処できるはずです。
この記事で紹介した「安全な場所」の選定基準や事前準備を参考に、あなたや家族が安全に過ごせるよう備えましょう。
まずは今できることから取り組み、大切な人を守るための最善の行動を起こしていきましょう。





